南野 一紀
イントロデュース
読者のみなさんのなかには、地方から都会に移住してきた経験がある方も、そうでない方もいると思いますが、地方で暮らしていた人間にとって都会というには恐ろしい化け物みたいな存在だと私は感じます。そんな経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか?
家族から離れても、家族の重圧がずっと自分を縛り続けている。いや、離れているからこそ縛り付けているのを感じる。そういったことを感じたことがある人もいるのではないでしょうか?
観念と現実の狭間で揺れ動いては、自らの存在に吐き気を催し、薬物に溺れる主人公の山田明。これはだれしもが共感するストーリではないと感じます。一部の読者は不思議な人の話として読むでしょう。そして、またある一部の読者は強い共感を持って、勇気づけられる人もいるでしょう。今回は純粋な観念論の敗北について書いていきたいと思います。
存在の悲劇性について考えさせられる本作は、中上健次氏の初期短編のなかでもかなりの傑作であると感じます。
「海へ」の評論で、中上健次氏本人については説明をしていますが、もう一度おさらいしたいと思います。
作者紹介
中上健次氏と言えば、コトノハ文学教室の講師であり、すばる文学賞の受賞作家でもある中上紀先生のお父さんにあたる人なわけですが、「中上健次っていったいどんな人なの?」と疑問にもたれた方のためにも、中上健次氏本人について語っていきたいと思います。
中上健次氏は和歌山県の新宮市出身の作家で、新宮高校卒業後、予備校を経て、羽田空港で肉体労働をしたのち、作家になった人物です。戦後生まれ最初の芥川賞作家としても有名で、『推し、燃ゆ』を書いたことで知られる、宇佐見りんも中上氏を尊敬しています。「中上健次以降の日本の作家の作品は文学じゃない」と言う人もいますし、「中上健次の死=日本近代文学の終焉」と言う人もいます。
予備校時代は、あまり勉強はしなかったようで、新宿にあったジャズ喫茶に入り浸って、悪い遊びをしながらジャズを聴きあさっていたのだとか。ジャズ喫茶ヴィレッジヴァンガードによく入り浸っては、友人と語り合ったという思い出は、ジャズ作品集『路上のジャズ』という本に克明に描かれています。その本のなかには、「鈴木翁二 ジャズビレ大卒」というエッセイもありますが、中上氏もまた「ジャズビレ大卒」だったのでしょう。結婚して、羽田空港で肉体労働をしたのちに、芥川賞を受賞し、有名作家になり、アメリカや韓国やフランスなどに滞在し、作家活動を展開しました。
中上氏のことを、「気性の激しい性格の人だった」と言う人もいますし、「ジェントルでやさしい人だった」と言う人もいます。人によって、作品も人柄も賛否両論がわかれる作家なんでしょうね。
一九九二年に他界された中上氏ですが、毎年、夏に「熊野大学」という和歌山県で行われる中上健次氏に関するセミナーには、多くの人が来ていました。
その他、本人に関することで言えば、晩年は対人恐怖が募って、自室からあまり出ない生活を送っていたという説もあります。
以上のことは、「海へ」の評論でも書いた作者自身についての説明ですが、ここからは中上氏の中編小説「灰色のコカコーラ」の評論に移っていきたいと思います。
あらすじ
和歌山県から都会に出てきたばかりの、山田明は予備校生だったけど、ほとんど予備校には行かず、ジャズ喫茶のRという場所に居座って、薬物をやり、その日を過ごしていました。明を取り囲む、ロビンやトコや森や少女などの登場人物は、まるで明になにか大切なことを伝えようとしているかのように見えます。
小説中では、夢とも現実ともつかないような描写や話が多く出てきて、どこまでが夢なのか、どこまでが現実なのか、そんな幻想に満ちた内容になっています。
本論
本作品のおもしろいところは、観念的にものを考えたがる「森」と「少女」、現実的にものを考えたがる「ロビン」と「トコ」と、その中間に位置している明の対比構造や、明の分裂した内面を投影させている幻想のように、登場するそれらの人物のどちらにも与できずにいる明の存在や、葛藤そのものがおもしろいと思います。
私個人は主人公の明以外では、登場人物の森という、昔の学生によくいるような観念的に物事を捉えたがる青年が一番おもしろいと思いました。
森は作品の前半で、宇宙と地上で起こっていることはシンクロニシティのようにしてつながっているという持論を滔々と述べます。つまり、宇宙というのはメビウスの帯のように、自分を呑み込んでもいるし、自分が呑み込まれてもいる、と言うのです。たとえば、腹が痛んだり、女性とセックスし、射精するということは、すごくフィジカルなことだけど、実はそうじゃなくて、同時に宇宙のどこかの星が爆発して、世の中は全て繋がっているんだという内容のことを述べたりもします。
つまり、森も現実を超越した受難を味わって生きているこということが、この話からわかります。そのあと、一度、仲間内で死んだという噂が立った森でしたが、実は生きていて、明に再度会ったときこんな話をします。
飯場で肉体労働をしている。労働というのは、肉体をドロドロにするということである。工場のタイムレコーダーを押しとき、言葉は単純になって、鈍器のように自分の身体を流れていて、その俺をわかって欲しいのだけど、馴れ馴れしくわかるなどという奴が現れたら、そいつを叩き殺してやりたい。
つまり、観念的だった森が現実の肉体労働に染まることによって、現実に回帰していく様を描いているのです。この作品に登場する少女もそうです。街頭で世界平和や人の不幸などを嘆いて演説などをしていたのですが、ロビンの運転する車に乗って、頭をぶつけメガネが割れ、額から血を流します。
つまりこの作品で描かれている一連の事柄には、観念的な思考をする自分を抹殺してやりたいという作者のメッセージが込められているのではないでしょうか。そしてなによりも、純粋観念の敗北が明にとって良きことであり、具体的現実性を帯びた観念やファミリーロマンスや薬物中毒になる悲劇によって、自分の存在の悲劇の抽象性を必死で薄めようとしている明の志向性が作中からは見て取れます。
人間はいつか大人にならなくてはいけないのです。
たとえ、存在の悲劇を生きるとしても、ずっと観念論を絶えず続けるわけにはいかないのでしょう。具体性を帯びた観念論や悲劇性を追い求める傾向にある中上文学は、初期の頃から、観念的でありすぎる自分や悲劇性によりエゴが肥大する罪や、そういった罪を抱えている自分に対する罰を加えようとするものだったのです。
なぜ作中において、純粋な観念論を持つ存在が一貫して、罰を受けなくてはいけないのでしょうか。それは中上文学において、純粋な観念論そのものが贅沢すぎるくらいの贅沢品であり、禁じられたものであるからなのではないでしょうか?
しかし中上文学のすごいところは、存在の悲劇性を保ちながらも、さらに自己否定や現実的な悲劇という名の罰をそこに加えることによって、むしろ逆に存在の悲劇性をより高尚なものに仕上げたところにあると思います。
これがアルベール・カミュや大江健三郎にはあまりなかった、中上文学の特異性であり、素晴らしい点であると感じます。
中上健次氏がもし長生きをしていたら、という話も愚問に近く、駆け抜けるように短い生を生きたことや、生命を燃やすように生き抜いたことそのものは、中上健次氏らしかったし、運命論的、決定論的に決まっていたことなのでしょうが、それでも、中上氏が長生きしていたら、ノーベル文学賞を受賞して、世界文学の頂点に近い位置にそのポジションを占めていたのではないかと私は感じています。
少なくとも、私にとって中上健次氏はノーベル賞の受賞ではたりないくらい偉大な作家であり、奇跡の存在であり、尊敬する人物であることには変わりはありません。
中上健次氏の「灰色のコカコーラ」ぜひ読んでみてください。
参考文献
・中上健次 『路上のジャズ』 初版 二〇一六年 中公文庫










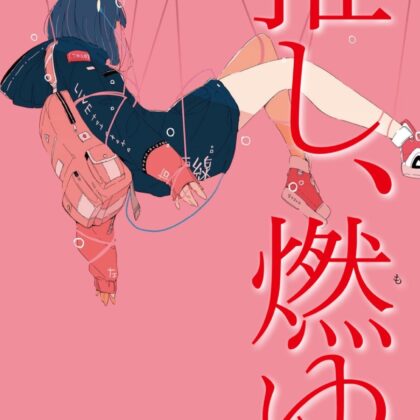




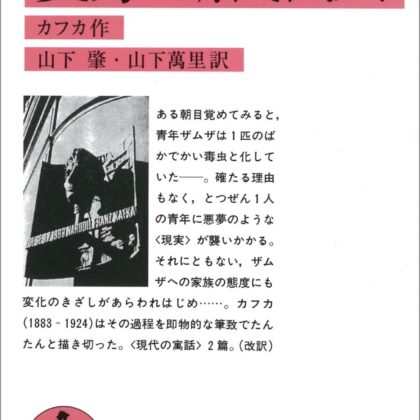
コメント